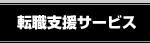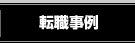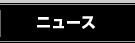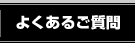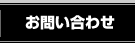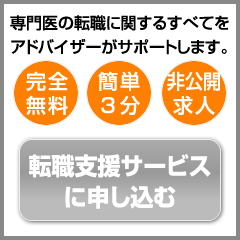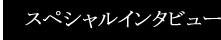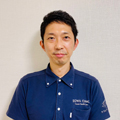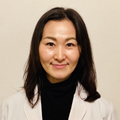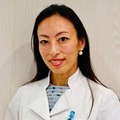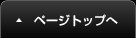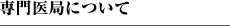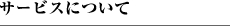日本脳卒中学会専門医
一般社団法人日本脳卒中学会
 | |
|---|---|
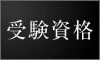 | 以下の①~⑥をすべて満たすものとします。 1)日本内科学会 認定内科医 日本小児科学会 小児科専門医 日本脳神経外科学会 脳神経外科専門医 日本医学放射線学会 放射線科専門医 日本救急医学会 救急科専門医 日本リハビリテーション医学会 リハビリテーション科専門医 のいずれかを有していること。 2)受験申請締切時点(2016年2月末日時点)で、日本脳卒中学会に在籍3年度以上 (2015年1月末日までに入会)で会費を完納していること。 但し、特例として本学会機関誌「脳卒中」あるいは日米合同誌 「Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases」に筆頭著者として掲載された論文がある場合に 限り日本脳卒中学会在籍期間1年度以上(2016年2月末日までに入会)であっても②を 満たすものとします。 ※初年度の会費を郵便局よりお振り込みされた日(郵便局側での処理日)が入会日となります。 3)日本脳卒中学会認定研修教育病院で、通算3年以上(受験申請締切:2016年2月末日時点で)の研修歴 (初期研修は含みません)があり、現在脳卒中診療に従事していること。 4)脳卒中患者を実際に担当した臨床研修歴の確認のため、脳卒中の病歴要約10症例の提出が必要です。 10症例のうち、 ◆出血性脳血管障害1症例、虚血性脳血管障害1症例を必ず含めること。 ◆「脳卒中」と判断が難しい症例(例:脳腫瘍内出血等)は含めないこと。が条件となります。 ※病歴要約は、研修教育病院以外のものでも可とします。 ※病歴要約の記載方法等は、受験申請書類を取り寄せしていただいた際にご案内致します。 この要約には教育責任者(診療科の長、あるいは日本脳卒中学会認定脳卒中専門医)の署名・捺印が 必要です。 病歴要約は事前に査読を行います。査読の結果、点数が基準に達しない場合には再提出となります。 病歴要約の評価点と試験での得点によって合否を決定します。 不正防止のため、受験者の中からランダムに選出し、病歴要約記載の患者が該当病院の患者で主治医も 間違いないか、病院長などの責任者に照会します。 5)日本脳卒中学会、日本脳卒中の外科学会もしくはこれらと同時開催されるスパズム・シンポジウムで、 1回以上筆頭演者として発表ないし講演していること。 ※STROKE2016で発表予定の場合も⑤を満たすものとします。 6)本学会機関誌「脳卒中」あるいは日米合同誌「Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases」に 1編以上(共著でも可)掲載されていること。または日本脳卒中学会誌以外の査読制度のある 学術雑誌に、脳卒中に関する原著論文もしくは症例報告が2編以上(共著でも可)掲載されていること。 ※病院紀要、商業誌への掲載は認められません。 ※受験申請締切時点(2016年2月末日)で論文が採択されていれば、In pressの状態でも申請可とします。(採択通知を受験申請時に提出して下さい。) |
 | 1)願書 2)医師免許証写、受験資格に示した専門医認定証写 3)学会発表抄録写と抄録集表紙写、論文最初の頁写 4)自験症例の病歴要約(脳卒中に関するもの)10例×2部 5)受験料の振込領収証のコピー |
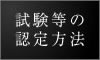 | 専門医試験はすべて筆答試験で、画像問題も含まれる。 |
| 注) | 当サイトでは情報の更新には努めておりますが、その内容を保障するものではありません。2017年、施行予定の新専門医制度によって科によっては大きな変化も予想されます。詳細に内容確認をされたい場合は、各学会にお問合せ頂きますようお願い致します。(2016年更新) |


専門医資格を最大限に生かした転職なら専門医局
専門医局の専門医資格取得方法の日本脳卒中学会専門医の取得方法のページです。
一般社団法人日本脳卒中学会の日本脳卒中学会専門医の制度の概要や、受験に必要な資格、提出書類、試験等の日本脳卒中学会専門医の認定方法をまとめています。
他の専門医の情報を確認されたい方は各専門医の一覧を掲載してありますのでご確認ください。

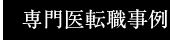
 |
救命救急科 男性医師 33歳
救急と麻酔科の掛持ちなんてあまり聞いたことがな... |
|---|
 |
形成外科専門医 女性(30代後半)
初月は患者様の引き継ぎなどで大変でしたが、事務... |
|---|
 |
内科専門医 女性 39歳
前職先より患者数は多いですがやりがいを感じてま... |
|---|
 |
人間ドック専門医 男性(50代)
正式にご就職が決まった後の準備期間中も、健診部... |
|---|

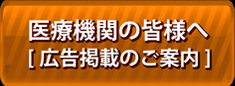


個人情報を扱うページではSSL通信で
安全性を確保しています。